産業医を選ぶ人事・労務担当者、経営者の方へ|自社に合う「嘱託産業医の選び方」6つの視点
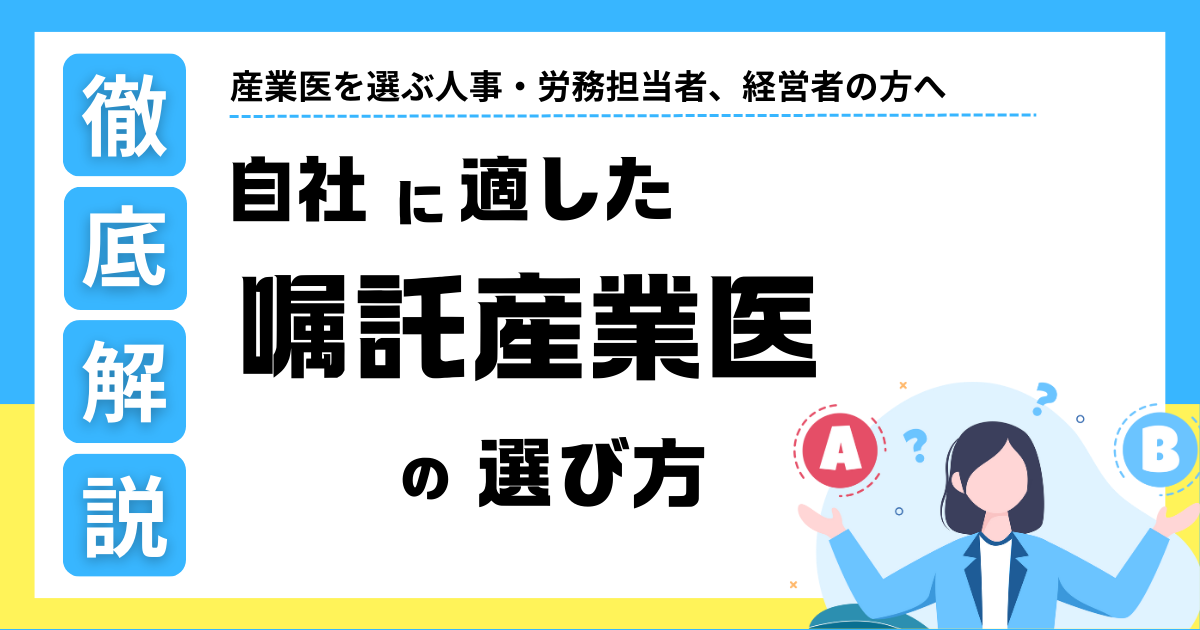
こんなお悩みありませんか?
- 「そろそろ嘱託産業医を入れる必要があるけど、何を基準に選べばいいのかわからない」
- 「前任の産業医が全く役に立たなかった…。次こそは失敗したくない」
- 「法令遵守の体制を整えたいけど、どこから始めればいいの?」
そんな悩みを抱える人事・労務・総務のご担当者さま、経営者の方は少なくありません。特に、はじめて産業医の選任が必要になった中小企業では、対応に迷うケースも多いのが現状です。
こんにちは。嘱託産業医としてこれまで30社以上を担当してきた産業医の本間です。
2022年に行われた日本産業衛生学会の企業向けアンケート調査によると、
「現在の嘱託産業医に満足している」と回答した企業担当者が重視していたポイントは、以下のような結果となっています(※1):
- 人事・担当者とのコミュニケーションがスムーズ(78.5%)
- 社員の相談に丁寧に対応してくれる(65.2%)
- 自社の状況や文化を理解しようとする姿勢がある(60.3%)
- 法令対応の確実性(54.8%)
- 衛生委員会や面談への積極的な参加姿勢(47.6%)
このように、産業医としてのスキルや知識だけでなく、「日々のやり取りのしやすさ」や「企業との協働姿勢」が、満足度に大きく影響していることがわかります。
本記事では、「働く人と会社の両方を支える産業医の選び方」について、現場経験に基づいた6つのチェックポイントをご紹介します。

- 企業対応力があるか(現場経験・人事連携)
- 相談しやすい雰囲気があるか(ざっくばらんに質問できる雰囲気か)
3. 対応スピードと柔軟性があるか(報告書やリモート面談など)
4. 産業保健スタッフと連携できる力があるか(チームで動けるか)
5. 自社の文化・従業員層にフィットするか(職場との相性)
6. 企業の今の課題に応えられるか(法令遵守+現場の悩みに対応)
1. 企業対応力があるか
嘱託産業医の資格や医師歴だけでなく、企業現場での対応経験があるかはとても重要です。特に中小企業では、人事や現場と密に連携できる柔軟性が求められます。
チェックポイント:
- 担当した企業の業種・規模は?
- 人事担当者との連携や、現場での面談経験は豊富か?
2. 社員・人事にとって「相談しやすい」雰囲気があるか?
社員や人事担当者が「相談しやすい」と感じる産業医の存在は、職場の健康を守るカギです。
メンタル不調や人間関係、健康上の問題は、早めの相談が深刻化を防ぐ第一歩になります。
だからこそ、フラットで安心感のある雰囲気がとても重要。
「こんなこと相談していいのかな」と迷う社員も多いもの。
だからこそ、産業医にはフラットで安心感のあるコミュニケーションが求められます。
また、ハラスメントや人間関係の問題、健康問題などは “話せる場” がなければ表に出てきません。
相談しやすい雰囲気は、社員の本音を引き出し、深刻化を防ぐ土台になります。
一方で人事担当者も、対応が難しい相談や機微な情報に悩むことが少なくありません。
そんな時、「この産業医になら任せられる」と思える存在が、現場の大きな支えになります。
また、産業医は社員の声に寄り添いつつも、企業の生産性や全体の公平性にも目を向け、
感情的に引っぱられすぎず、中立的な立場での“落とし所”を意識することも重要です。
さらに重要なのは、休職・復職支援やメンタルヘルス対応、両立支援など、社員と企業の利害が交差する場面で、双方の視点を踏まえた“納得感ある調整”ができるかどうか。
単なる聞き役にとどまらず、現場の状況に応じたWin-Winの解決策を模索できる産業医は、企業の中で大きな信頼を得る存在となります。
相談のしやすさは、企業にとって“健康経営”と“リスク回避”の要となります。
当事務所では、そんなバランス感ある関わりを大切にしています。
チェックポイント:
- 面談時のコミュニケーションスタイルはフラットか?
- ハラスメントやメンタル不調に寄り添う姿勢があるか?
- 社員側、会社側双方のWin-winを考慮して中立的な立場での落とし所を柔軟に姿勢があるか?

3. 「対応スピード」と「柔軟性」があるか?
産業医に求められるのは法令遵守だけではありません。たとえば、急な面談対応や報告書作成に迅速に応じられるか、リモート面談などにも柔軟に対応できるかは、スムーズな問題解決には重要な要素です。
チェックポイント:
- 面談スケジュールの調整や報告書の提出スピードは?
- オンライン対応や柔軟な調整に対応できるか?
4. 衛生管理者・保健師などと「チームで動ける」か?
産業保健は一人では完結しません。保健師や人事との協働意識がある産業医ほど、チームで問題解決に当たれるため、対応範囲も広がり、スピード問題解決能力も高まります。
チェックポイント:
- 会議・衛生委員会で周囲の意見を引き出しているか?
- 他職種と積極的に連携しようとする姿勢があるか?
5. 「企業文化」や「従業員層」にフィットするか?
たとえば、工場の現場とIT企業のデスクワークでは、職場の課題も雰囲気もまったく異なります。その会社に合った“人柄”や“感性”を持つ産業医であるかどうかも、大きな選定ポイントです。
チェックポイント:
- 社員の年齢層や性別構成に合った対応ができそうか?
- 自社の価値観や文化になじみそうな雰囲気か?
6. 企業の“今の課題”に応えられるか?
最近は「法令遵守の体制を整えたい」「メンタル不調者の対応で困っている」「離職が多く職場改善したい」など、緊急性の高い課題を抱える企業も増えています。
そんな時こそ、課題に合った柔軟な提案やサポートができる産業医が必要です。
特にメンタルヘルス不調者の復職や、治療と仕事の両立支援、ハラスメント対応など、社員と企業側の利害がぶつかる場面では、冷静に状況を整理し、双方の納得解を探れる力が問われます。
一方的な“擁護”や“指摘”に終わらず、対話を通じて建設的な合意形成を図れる産業医こそ、企業の「伴走者」として真価を発揮するのです。
チェックポイント:
- 法令対応に加え、混沌とした現場課題にも耳を傾けてくれるか?
- 「とりあえず相談してみよう」と思える安心感があるか?
- 多様なケースに対応できる“引き出し”があるか?
【まとめ】失敗しない産業医選びのコツとは?
嘱託産業医は「資格があれば誰でもいい」わけではありません。
法令対応+現場力+相談しやすさの三拍子がそろった産業医を選ぶことで、会社と社員の両方を守る“頼れる存在”となります。
私は、「働く人が不幸にならない職場づくり」をテーマに、産業医活動を行っています。
そして最後に、ぜひ覚えておいていただきたいのは、産業医は“毎月会う存在”であり、継続的にやりとりを重ねるパートナーであるということ。
だからこそ、
- 「やりとりしやすい」
- 「フィードバックや要望を受け止めてくれる柔軟さがある」
- 「関わることで社内が少し明るくなる」
――そんな産業医を選ぶことが、結果的に企業全体の産業保健活動を“前向きで、実りあるもの”にしてくれます。
“活動が楽しくなる産業医”というのは、あまり聞き慣れないかもしれませんが、実際にそのような産業医がいると、衛生委員会や健康相談の場が前向きに機能し、職場の空気が変わるきっかけになることも多いのです。
「この人となら、毎月会いたいと思えるか?」――このような直感も、実はとても大事な選定ポイントなのかもしれません。
「自社に合う産業医を探したい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
※1:出典「企業における産業医に対する期待と実態に関する調査報告書(日本産業衛生学会 産業医部会 2022年)
 産業医フォレスト先生
産業医フォレスト先生東京駅周辺、丸の内、八重洲で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
千代田区、文京区、豊島区、中央区で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
大手町、御茶ノ水、神保町、池袋、新宿、銀座で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
ぜひお気軽にお問合せください。
女性産業医が、御社のご要望に応じて、健康経営やメンタルヘルス支援にきめ細かく対応いたします。
全国の50名未満の会社様には、オンラインでの産業医サービスも行なっております。
(男性産業医も在籍しておりますので、ニーズに合わせて対応いたします。)

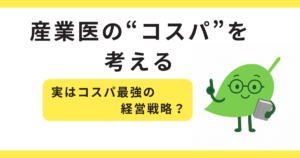
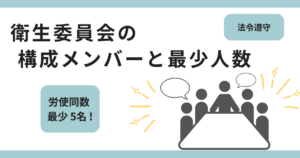
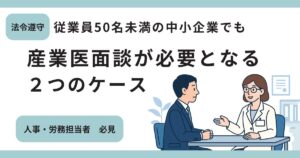
コメント