女性社員の離職が続く理由とは?育休復帰・静かな退職・ワークエンゲージメントを女性産業医の視点で解説
【制度はあるのに女性社員が辞めるのはなぜ?】
静かな退職とワークエンゲージメント低下を防ぐ“産業医の視点”
「育休復帰後の社員が、特に不満も見せずに辞めてしまう」
「時短や在宅勤務、配慮など制度は整っているのに、なぜか女性社員の離職が続く…」
こうしたお悩みを、人事ご担当者からよく伺います。
今回は、実際の相談内容をもとに、「静かな退職」や「ワークエンゲージメントの低下」の背景にある職場環境、
そして産業医が“健康支援の範囲内”でできることについてご紹介します。
優秀な女性管理職の“静かな退職”とその連鎖
 200名の会社の人事 鈴木さん
200名の会社の人事 鈴木さん実は最近、うちの女性管理職が育休から復帰して半年で辞めてしまって…。
すごく優秀な方だったのに、“不満はないけど、このまま働き続けるイメージが持てない”って。



“静かな退職”ですね。
健康状態に大きな異常はなくても、“働きがい”や“期待されていない感覚”が続くと、
自然と離職につながるケースがあります。



その後、仲の良かった別の女性社員も立て続けに退職して…。
時短制度や在宅勤務・配慮など制度も整えていたのに、何が悪かったのかよくわからなくて。



“制度がある”と“活用されている”は別物なんです。
特に育児と仕事を両立する女性社員は、配慮のつもりで仕事から外されることで
“必要とされていない”と感じてしまうことがあります。
ワークエンゲージメントとは?
“ワークエンゲージメント”とは、社員が健康にいきいきと働く状態を示す概念で、以下の3要素から成り立ちます:
活力(元気さ)
熱意(やりがい)
没頭(集中できる状態)
オランダのユトレヒト大学の研究では、エンゲージメントの高い社員は生産性が高く、離職率も低いことが示されています(Schaufeli & Bakker, 2004)。
参考:Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004).
Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement
Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293–315.
このような問題に、産業医は健康管理の視点から対応が可能です。
健康管理の視点から見た“働きづらさ”の兆候
まず大前提としてお伝えしたいのは、
産業医は業務内容や人事制度の設計・評価には関与しません。
これらは企業の判断と責任に基づくものであり、産業医が指示や決定を行う立場にはありません。
私たち産業医が担っているのは、
「働き方や職場環境が、健康にどう影響しているか」
「その状態が続いた場合、心身にリスクがないか」
といった 健康管理の観点からの“気づき”や“助言” です。
健康視点から“働きづらさ”に気づきやすくなる
たとえば、以下のような兆候を早期にキャッチし、企業に共有することで、
重症化の防止や定着支援につながることがあります。
- 復職後、業務量や責任の変化によって体調の乱れや疲労が蓄積しやすくなっている
- 配慮の結果として “やりがいの喪失” や “職場からの孤立感” が強まっている
- 業務負荷や通勤時間の長さにより生活リズムや睡眠が乱れている
これらはすべて、明確な病気ではなくても、健康を損なう前段階として注意すべき変化です。
こうした点に気づける “第三者的で医学的な視点” を持つ人がいることが、企業にとっての安心材料になります。
ワークエンゲージメント低下の予防も、健康支援の一環として
ワークエンゲージメント(活力・熱意・没頭)の低下は、
ストレスやメンタルヘルス不調の初期兆候と重なる部分があります。
そこで産業医が行える健康支援は以下の通りです:
● 配慮=除外にならないよう注意喚起
「無理しないで」という言葉が、「もう期待されていない」と受け取られてしまうケースもあります。
→ そのニュアンスの違いに気づける視点が、職場全体の安心につながります。
● 小さな変化を拾う仕組みをサポート
面談や職場巡視を通じて、本人も言葉にしづらい違和感や疲労感を早期にキャッチします。
● 業務負荷や働き方の影響を医学的に観察
睡眠・食欲・体重・集中力の低下など、“見えない不調”の前兆を医学的に見立てて企業に共有します。
不調の社員に気づく方法は法的にも定められています
実際に産業医がどのように社員の不調に気づき、対応しているのか?
厚生労働省の産業医活動ガイドライン等に基づく、具体的な実務の流れは次の通りです。
🟢 ステップ① 不調の“兆候”に気づく場面
- 健康診断・長時間労働面談の結果確認
→ 疲労蓄積や睡眠障害・生活習慣の乱れが見られた場合 - ストレスチェックの集団分析
→ 高ストレス部署やコミュニケーションの問題があるチームを把握 - 人事・上司からの報告を受けた個別対応
→ 「最近元気がない」「会話が減った」などをきっかけにフォローを提案
🔵 ステップ② 面談と健康上の配慮提案
- 産業医面談の実施(本人同意のうえ)
→ 睡眠・集中力・気分の変化、家庭状況との両立などをヒアリング - 就業上の医学的意見書の作成(必要時)
→ 「一時的な短時間勤務推奨」や「静かな作業環境での業務」など - フォロー面談の実施
→ 状況が改善したか、追加支援が必要かを段階的に確認 - 職場環境への助言(必要があれば衛生委員会等へ)
→ 同様の不調者が複数いる場合、業務負荷や配置バランスについて提案
・労働安全衛生法第13条・14条
・厚労省「産業医活動ガイドライン(2023年)」第6章
・ストレスチェック制度実施マニュアル
「医療と職場の橋渡し役」として
産業医は、「働き方による健康への影響」について、
医学的見地から見立て、リスクがある場合には適切に企業へ伝えることができるという意味で、
社員にとっても企業にとっても、安心感につながる存在であると考えています。
まとめ:健康で働き続けられる職場の実現に向けて
育児や介護と仕事を両立する社員の離職には、制度の不備よりも“活かされない空気”が関わっていることもあります。
それに早く気づき、過剰ではない範囲で助言できる体制があること。
それが企業にとっても、社員にとっても「続けられる職場」づくりの第一歩となります。
【ご相談のご案内】
丸の内フォレスト産業医事務所では、女性産業医による解像度高い女性就業支援が可能です。
復職支援・健康配慮の面談・職場改善への医学的助言など、
一次予防を軸にした産業保健支援を行っております。



東京駅周辺、丸の内、八重洲で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
千代田区、文京区、豊島区、中央区で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
大手町、御茶ノ水、神保町、池袋、新宿、銀座で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、
ぜひお気軽にお問合せください。
女性産業医が、御社のご要望に応じて、健康経営やメンタルヘルス支援にきめ細かく対応いたします。
全国の50名未満の会社様には、オンラインでの産業医サービスも行なっております。
(男性産業医も在籍しておりますので、ニーズに合わせて対応いたします。)

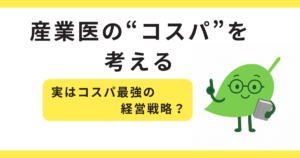
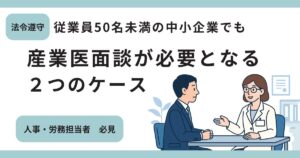
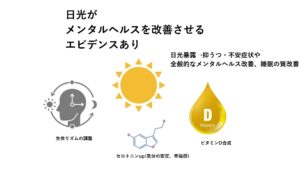
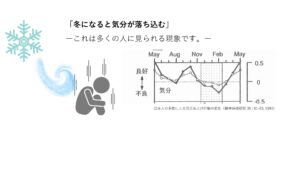
コメント